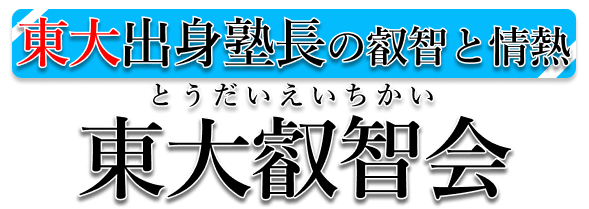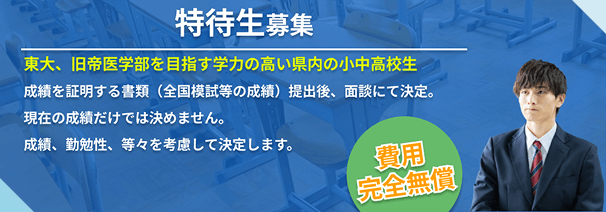2025.5.15
塾は普通真面目に通えば大体は成績が伸びるものだ。これは当然である。勉強時間が塾で学んでいる分は増え、丁寧な解説の教師なら「わからない箇所、自力で解決できない箇所」を教えてくれるのだから成績の伸びは当然である。しかし当然全員がそうではない。成績が伸びない場合、保護者は塾になぜ成績が伸びないのかを聞くべきである。入塾後3ヶ月位の後が良いと思う。正確に言えば普段から塾側と保護者側は緊密に生徒の成績について情報交換を行わなければならない。筆者が経験した典型的な成績が伸びない、つまり塾で、そして家庭で真剣に勉強していないパターンには次の様なものがある。あくまでも一例ではあるが。
①教材プリントがカバンに入れっぱなし、くしゃくしゃになり全く復習の形跡がない。復習しなければ、記憶に定着出来ないので当然成績は伸びない。これは非常によくある一般的なものだ。
②やたらとトイレ休憩が多い。15分ー30分に一回位トイレに行く子がいる。病気の可能性もあるので保護者に聞いてみても、自宅では全くそんな傾向は無いとう話で一軒落着。要はトイレ休憩である。ただし入塾間もない時によくあるが、自然に直ってくる場合もある。
③忘れ物が多い。復習用のプリントまたは解説途中のプリントを何回も忘れてくる。自宅で復習していないので忘れてくるという単純な話である。
④通塾曜日がころころ変わりやすい。先週は月等日だったのが、今週は火曜日になる。勿論これは部活だったり体調だったりがあるので、時々は可であるが頻度が高ければ、気分次第で「今日は塾休もう」になるわけだ。
⑤個別教室では今まさに必要な課題をやるわけだが、緊急性の有る子(苦手科目や分野がある子)に限って「今日は学校の宿題やっていいですか?」となる。教師はここをやるぞと張り切っているので落胆が大きい。勉強時間を確保していないので宿題さえ塾でやらねばならない位自宅学習の習慣が出来ていない場合である。
⑥塾で明らかに眠そうだったり、疲れていたりする様子の場合。ここ沖縄では非常に多い。子どもの夜ふかしはもはや沖縄では普通のことである。筆者は教えるエネルギーの何分の一かは睡眠指導に当てている。たまに「6年生の今でも夜9時にはきちんと寝かせています。」という保護者の方に面談で会うと感動ものである。口うるさく嫌われても「早く休みなさい」と言い続けるしかないのだ。子供に正しい生活習慣をつけるのは親の大事な仕事である。