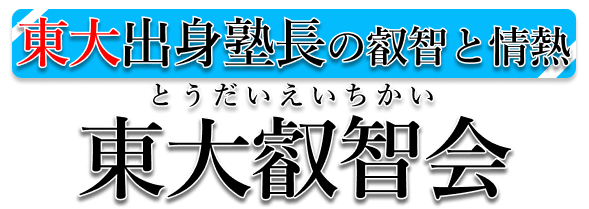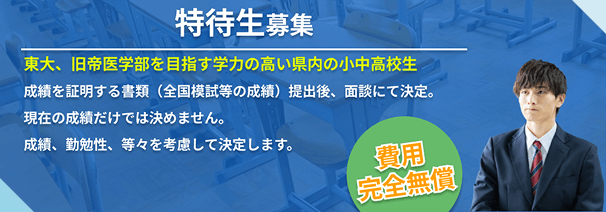2025.9.17
今回は塾業界の内輪話である。不愉快に感じる方は読まないで頂きたい。筆者が沖繩に移る前に教室を開いていた都市は、人口が急増して、多くの塾が乱立状態であったが、個人経営であったり、数名の教師の雇用のみの比較的小さな塾はお互いの情報を交換して、生徒指導の糧としていた。そういう数十の塾の代表で中学や高校を一緒に訪問して、生徒達にその情報を還元したことも懐かしい思い出である。沖繩ではこういう横の繋がりが無いので、情報は断片的になり易い。年配の先生が引退される時に生徒を引き受けたり、遠距離通塾の生徒は生徒の近くの信用できる塾に紹介したりしたこともあった。閉塾(塾がなくなる)の場合、そこで働かれていた教師を雇用したこともある。自賛であるが、筆者の教室では、雇用の条件はかなり、他塾に比べ良かったと思う。講師希望者は常に多かった。フランチャイズ教室の倍額以上の講師料を支払っていた。授業料は平均的だったので規模に比べて筆者の収入は少なかった。経営者としては失格だったかもしれない。
最近はフランチャイズ塾を中心として(しばしば経営者は教育業界の人でなかったりする)雇用の条件が著しく悪い。時給1000円などと書いてある。ひどい場合は試験雇用と称し、1000円以下である。来年以降は最低賃金法に触れる恐れさえあるのだ。また時間給でなく、定期雇用の場合も20万円に満たない事がしばしばである。雇用の条件も14-22時と書いてあるが、22時過ぎにも指導記録を遅くまで書かせたり、他の教師との反省会を開かせたり、」遅い時間の保護者との面談等々で日常的に賃金が発生しない(させない)時間が多い。残業代がかからないのである。定時の出勤時間前にノルマと称し塾のチラシ配りをさせたり、ひどい例になると働く時間を50分と規定して、生徒の質問を受ける休み時間10分は賃金が生じないやり方の経営者もいる。一体いつの頃から塾業界はこんなブラックな業界になってしまったのだろうか?最大の要因は経営優先のフランチャイズ塾が増えたことであろう。数百万から数千万の初期投資を回復するにはまずは人件費を少なくすることであろう。塾業界の人材不足という話は聞いたことがない。安い賃金でも働く子供が好きな人は必ず存在する。そういう中でも素晴らしい指導力を発揮する方がいる。こういう人達の為に、雇用条件の改善が絶対に必要だ。行政が果たすべき仕事があるに違いない。