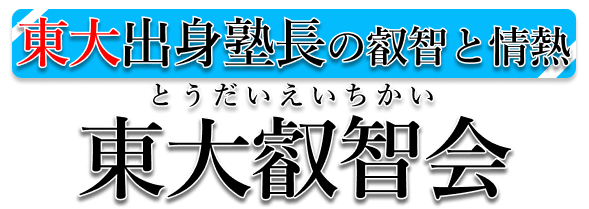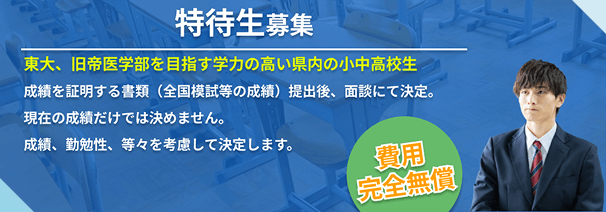2025.7.10
長年教えていると数学(中学受験なら算数)の出来る子達には一定の同じ傾向があることに気づく。其の特徴は以下のようなものである。読んで頂いてる方で思い当たるフシ=実感があれば既に数学が得意か、あるいは得意に出来る可能性があるかもしれない。尚ここでの数学の問題自体、公立中学の定期試験や、小学校の教科書確認テストの様なものではなく、全国レベルの模試を想定した話である事はご理解頂きたい。
① 問題が配布されると、いきなり解かず、まず全体を見回して、大問1ー2辺り(通常基礎標準難問の順に並んでいる場合)を確実に抑えて、残りは何番を解けば合格ラインに達するか、全体の見通しが出来る子達は確実に数学が出来る子である。
② ①の真逆は必ずいきなり何の見通しも持たず、いきなり計算を始めてまるで満点狙いであるかのように、闇雲に最初から解いていって、後半の配点が大きい問題の前に時間切レになる子達である。この子達の頭の中では、数学=計算という考えが支配的である。
③ 数学の出来る子達は何とか問題を図形やグラフに出来ないか考える子達であり、数学の本質が問題の設問を与えられた条件を入れて(情報化)視覚化する事であることが理解出来る子達である。
④各問を解く前に視覚化しながら5ー10分くらい見通しを立ててから計算を始める子は確実に数学のセンス(センスが無くともセンスが有る子達や教師の指導が良ければ出来るようになる)がある。
⑤ 数学を単に問題を解くことではなく、ゲームのように楽しく解けたら賢くなって得をした位に楽しめる子達。この子達に数学の歴史や、歴史上の有名な数学者のエピソードを話す事は筆者の至福の時間だ。数学好きの子たちは目を輝かせて聞いてくれる。数学は究極好き嫌いが影響する教科である事は間違いない。其の本質は楽しめるか、数学から数楽に出来るかであろう。数学嫌いの人の定番の考えは「数学なんて生活で何の役にも立たない」である。数学は確かに生活にすぐには役に立たないであろうが、そこで鍛えた頭脳は万能で一生使うことが出来る事確実である。